

塾長インタビュー vol.2 Date.
これからの社会と
世界のために
慶應義塾ができること
「デジタルネイティブ世代の塾生たちの声にもしっかりと耳を傾け、次代の『先導者』として活躍するための環境や土壌を整える」
AI革命の渦中にある現在、どのような社会(世界)を構想し創造していくか、
2025年5月27日から2期目に突入した伊藤公平塾長が、
慶應義塾をサスティナブルな組織として未来へつなげていくためのビジョンを語ります。
塾長として2期目を迎えられ、1期目の振り返りと塾長として感じられた思いを率直にお聞かせください。
伊藤
2021年就任から、数々の仕事に取り組みましたが、就任時の新型コロナウイルス感染症拡大とワクチン接種への取り組みはやはり忘れがたい記憶として残っています。
医療従事者や高齢者などからワクチン接種が始まり、やがて企業や教育機関での「職域接種」が始まりました。教育機関として国の「職域接種」の要請に最初に手を上げたのが慶應義塾でした。
「コロナ禍で奪われたキャンパスライフをなんとしても取り戻したい」という私の願いに、多くの義塾関係者がご賛同いただき、北川雄光常任理事をリーダーとするプロジェクトがスタートしました。医療従事者の確保から物資のロジスティクス、予約システムや接種会場における動線設計などを驚くべき速さで行い、わずか1ヶ月半足らずで1日約4000人規模の接種体制を整えることができました。実に見事なチームワークでした。


職域接種は慶應義塾の枠を超え、他大学にも範囲を広げました。当時、欧米を中心に海外留学をするにはワクチン接種が義務付けられ、留学を断念せざるを得ない学生が続出していたからです。彼らの学びの機会を取り戻すことは、医学部、看護医療学部や薬学部、大学病院を持つ慶應義塾としては重要な使命であると考えました。
約5万人への接種を完了後、私は改めて義塾関係者の献身と組織力に感嘆させられ、それぞれが自らの役割において最大限の力を発揮できる人々の存在こそが慶應義塾の根幹を支えているのだと痛感しました。また、その間には日頃から慶應義塾を応援してくださる塾員などの義塾関係者から、大学病院へマスクやガウンなどの物資のご提供や、ご寄付による多大なるご支援もいただきました。改めて心より感謝申し上げます。
教育機関として国の「職域接種」の要請に
最初に手を上げた

慶應義塾を強くサスティナブルな組織として未来へつなげていくためには、どのような取り組みが必要だとお考えですか。
伊藤
1期目から変わらぬ私のテーマは「グローバルに開かれた慶應義塾」の推進です。
多くの慶應義塾の研究者がグローバルに活躍してきたおかげで、世界中の識者たちが私たちのキャンパスを訪れたいと言ってくれます。
例えば2023年にOpenAI社CEOのサム・アルトマン氏、2025年になって欧州委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエン氏、『サピエンス全史』の著者ユヴァル・ノア・ハラリ氏をはじめとするそうそうたる方々がキャンパスを訪れました。他にも多くの世界のトップリーダーが来塾し、講演だけでなく教員や学生と親しく交流しています。

こうした世界から注目される教育研究機関であるために、グローバルに活躍する研究者のバックアップを行うとともに、私自身も各国の大使などと情報交換をしながら、慶應義塾のポテンシャルをアピールしています。世界に開かれ、世界で活躍できる「人」を育てるために、グローバルな視野で慶應義塾のプレゼンスを高めることは必要不可欠な取り組みであると考えています。
多くの世界のトップリーダーが来塾し、
講演だけでなく教員や学生と親しく交流

OpenAI社CEO
サム・アルトマン氏

欧州委員会委員長
ウルズラ・フォン・
デア・ライエン氏
OpenAI社がリリースしたChatGPTを始め、現在、生成AIが目覚ましい進化を遂げて、社会のあり方を変えようとしています。
伊藤
生成AI登場のインパクトはかつての産業革命に匹敵するでしょう。「AI登場以降にどのような社会(世界)を構想し、創造していくか。」今後の教育や研究の在り方を考えるにあたって、それが一つの前提条件となります。
慶應義塾は総合大学として幅広い研究を行う最高の学者が揃っています。この環境を活かし、さまざまな視点から「AI革命」後に社会で活躍する世代を見据えた教育・研究環境の整備も継続的に取り組んでいきます。私たちはこれまで以上に塾生たちの声に耳を傾け、彼らが次代の「先導者」として活躍するために必要としているモノ・コトを知ることが大切だと考えています。
「先導者」という言葉は必ずしも革新的なトレンドを先取りすることを意味しません。場合によっては、故きを温ねることもあるでしょうし、当たり前のことをしっかりやり遂げることで達成されるケースも少なくありません。大切なことはぶれない志を持ち、同じ志を持つ仲間との信頼関係を築き、コモンセンス(常識・良識)に基づく行動とそれを導く「人間性」です。私はそれこそが慶應義塾の精神だと考えています。
幕末、福澤諭吉は19歳で長崎で蘭学を学び始め、それから10年以上、30歳頃までは洋行を含めて時代の激しい変転の中で、これからの日本のあるべき姿を見据えながら、ひたすら学びの日々を送りました。AI革命の最中に生きる若い世代にもぜひ福澤のように学び続けてほしいのです。大学は決して就職予備校ではありません。時代の風を浴びながら生きた学びを得る場です。大学院教育も含めて次代に求められる教育に関して、私は慶應義塾長として「私たちが考える次代の大学・大学院教育」について産業界も含めて広く社会への提言を行っていきたいと考えています。
今後、慶應義塾と塾員とのつながりを今まで以上に重視していきたいと考えられているとうかがっています。
伊藤
はい、前述のコロナ禍における「職域接種」のプロジェクトにおいて実感しましたが、慶應義塾が今後、国内外でのプレゼンスを高めていくために、社会のあらゆる分野で活躍する塾員の存在は必要不可欠だと考えています。三田会はもちろん、卒業後に慶應義塾とのつながりが薄れていた塾員との関係を深めることも大切になってくるでしょう。
そのためには、卒業後の塾員同士の交流や塾員がキャンパスに足を運ぶ機会を増やしていきたい。たとえば従来の卒業25年・50年塾員招待会に加えて、他にも同期の塾員が集う機会などを作っていきたいと考えています。

卒業5年塾員招待会

あるいはリアルな交流以外でもICカードやアプリなどデジタルの力を使用して塾生、塾員、教職員がつながる仕組みなど、さまざまな形で「慶應義塾社中」を再構築できればと思っています。
さらに義塾関係者以外にも慶應義塾の特色や魅力を広く知っていただく新しいメディアなども構想中です。
慶應義塾の特色や魅力を知る
社会は大きな変革期を迎え、一方で混迷する世界を良くするためにも、慶應義塾という組織が社会や世界に貢献できることは、まだまだたくさんあると私は確信しています。ぜひ皆さんの力をお貸しください。
次代の「先導者」を育む環境づくり、
そして社会との
強い絆づくりを目指す、
慶應義塾の多様な挑戦に
ご期待してくださる皆様へ
慶應義塾では、グローバルに開かれた教育、
先進的かつ創造性あふれる研究、
更なる医療の発展に向けた様々な寄付を募集しています。
ご興味を持たれた方は、基金室Webサイトを是非ご覧ください。
注目の記事
Featured articles
-
Date.
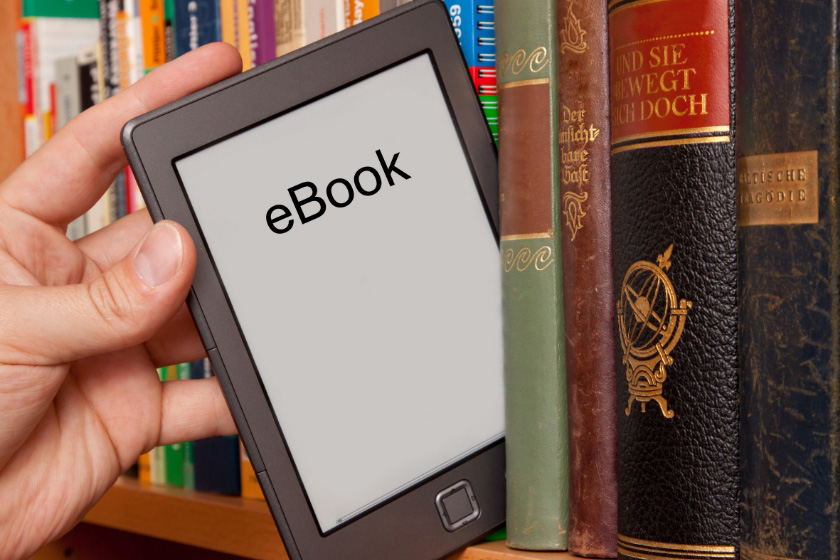
#教科書サブスク化
#SDGs
#ビジネスの現実
教科書のサブスク化で資源を守りたい
SDGs実現の主役は塾生!塾生主役の選抜プロジェクト・「塾生会議」の挑戦
-
Date.

#医療改革
#がんゲノム
#一生涯の医療フォロー
DNA情報を分析し、がんや難病の患者さん、一人ひとりにあわせた医療を
命を救う“最後の砦”が進める医療改革
-
Date.
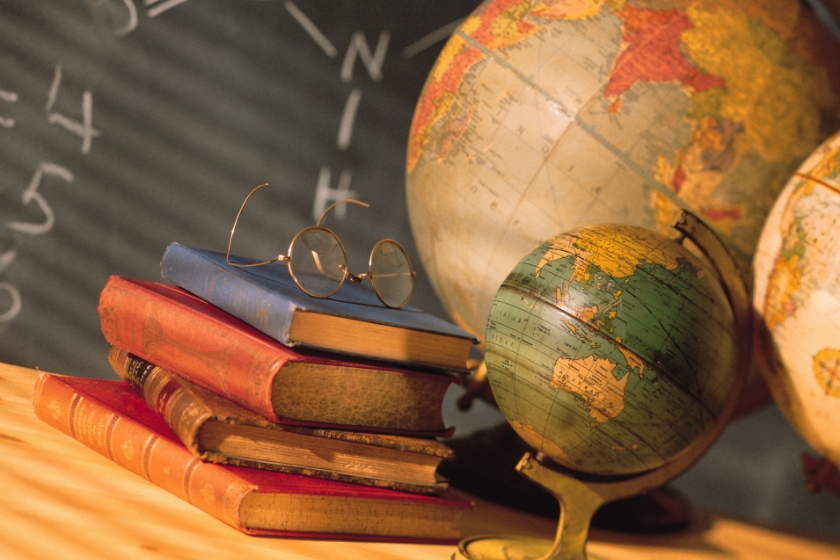
#世界大学ランキング
#国際化
#世界のKeio Universityを目指して
“グローバル化”と“国際化”、その違いは多様性と人材交流にあり
レピュテーションの向上で実現する世界のKeio University
-
Date.

#卒業しても利用できるあの施設
#こころの故郷
#未来のキャンパスのあり方
義塾社中の誰もが過ごしやすい場所を目指して
塾員なら知っておきたい!進化を続ける大学キャンパスの今社中交流の要、大学キャンパス活用のすゝめ
Keio University SPECIAL SITE





