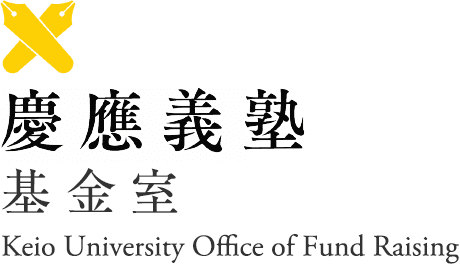維持会奨学生VOICE
2025年度維持会懇話会に参加された維持会奨学生を代表して、10名の奨学生の声をお届けします。
彼らの熱意と努力、そして未来への展望に迫ります。



①維持会奨学生として思うことは?
②一番興味のある授業は?
③今後、学生生活でチャレンジしたいことは?
④卒業後の進路、将来の夢は?
北海道出身 法学部2年
①今年度、慶應義塾維持会奨学金奨学生に採用していただいたことを、大変光栄に思います。私自身、これまで学費や生活費の支払いを全て貸与型奨学金に頼っており、学業に対して金銭的な不安がありましたが、維持会会員の皆様のご支援のおかげで多くの時間を勉学に充てることができるようになり、非常に充実した、心の底から楽しいと思える学生生活を送らせていただいております。学費を得るためアルバイトに多くの時間を割かずを得ず、学業に思うように力を入れられないこともあり、とても悔しく思っておりましたが、この度の皆様のご援助により学びたいという意欲を金銭的に後押ししていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。奨学生の名に恥じぬように、そして将来社会に貢献できる人間になれるよう、一層邁進して参ります。
②私が現在最も興味のある授業は、「地域社会論Ⅰ」です。私は地方で生まれ育ったということもあり、地域創生や地域社会といったことに非常に興味があります。この講義を通して学んだことは、「地域づくり」には住民の意思と持続可能性が不可欠であるということです。行政が地域開発を行なって経済が活性化したりそこに雇用が創出されたりしても、それが住民の意思を無視した開発であれば、地域の歴史や文化、日常生活までが崩壊してしまう可能性があります。利害調整を図ることは難しいことですが、長期的な視点を持って、持続可能な仕組みは何かということを生活者が考えていくことが大切だと感じました。自分が生まれ育った環境のことを学問として学ぶことは非常に面白く、学んだ知識を将来、地元や地方に還元できるようになりたいと思います。
③今後の学生生活の中で、私は語学の学習と政治学などの興味のある学問の知識を増やすことに力を入れていきたいと思っています。語学に関しては、来年度以降ゼミに所属し本格的な研究活動をしていく上で必須だと思うので、TOEFLやIELTSなどで高スコアを取得できるように日々の学習を頑張っていきたいと思います。また大学に入り新たにフランス語の学習もしているので、実際に使うことができるくらいの実践力を身につけたいです。そしてそれだけではなく、慶應義塾の政治学科という恵まれた環境で学ばせていただいていることの利点を最大限生かし、授業で得た知識を本当の意味で自分のものとすることができるよう、何度も復習したり関連文献を読んだりして知識の増強に努めていきたいです。
④卒業後は、行政、あるいはメディアやシンクタンクなど、政治に関わるさまざまな仕事を視野に入れ、社会に貢献できる道を模索していきたいです。特に、現場の声を反映させる政策づくりに関心があり、国民の生活をより良くするための仕組みを考え、実現することに携われる仕事を目指しています。そして、将来的には地元に戻り、それまでに培った知見や経験を活かして、地域の活性化に貢献したいと考えています。北海道は広大な自然や豊かな文化を持ちながらも、人口減少や経済の停滞など多くの課題を抱えています。私は、大学卒業後はまず日本や世界のさまざまな地域で経験を積み、政治や社会の仕組みをより深く理解した上で地元に戻り、地域に根ざした活動を展開したいと考えています。
栃木県出身 法学部1年
①率直にうれしいです。自分の家庭では妹が身障者で母が付き添いで介助しており、働く時間が取れないこともあり、経済状況が芳しくないため学費の負担が大きかったです。しかし、維持会の皆様の支援のおかげでその負担も軽減され、心おきなく勉学に励めています。また、通学に長時間かかるため、アルバイトする時間を捻出することが厳しいですが、その心配もなくなり、時間に余裕が生まれ、勉強や課外活動などのさまざまなことに精力的に取り組めており、充実した学生生活を送れています。法律学科の授業や語学、一般教養の授業はどれもレベルが高く苦戦していますが、奨学生としての自覚をもってこれからも精進していきます。
②民法の授業に特に興味をもって取り組んでいます。民法の授業は、総則と債権各論の二種類があり、学説と判例の立場に照らし合わせて様々な状況について学びます。専門用語ばかりで構成されていたり、状況が複雑で複数の場合分けが必要であったり、受講している授業の中で一番難しく感じていますが、民法の極力落ち度のない人の権利を保護できるように工夫されているところや条文の解釈が一つに定まらない点が奥深く、とても魅力的に感じます。将来民事を中心に取り扱う弁護士を志していることもあるので、引き続き民法の授業は力を入れて取り組み、ゼミも民法関連のものを選びたいと考えています。
③今後学生生活で取り組みたいことは主に二つです。一つは国際交流です。私は中学生のとき、住んでいる那須塩原市の姉妹都市であるオーストリアのリンツ市に、市の海外派遣事業でホームステイしました。その時の経験がきっかけで第二外国語としてドイツ語を履修しており、ドイツ語を活用できるように日々勉強しています。今は初学者コースですが、二年次には発展的なコースの履修を考えています。また、ドイツ語圏への短期留学にも取り組みたいです。もう一つは落語です。入学前から興味のあった落語研究会に入部しました。老若男女問わず笑顔にできる落語ができるように練習していきます。
④卒業後は司法試験予備試験の合格またはロースクールの卒業を経て司法試験に挑戦し、弁護士になりたいです。弁護士として経験を積んで独立後、当事者の家族として身近で体験していたことを活かし、障碍者など社会的立場の弱い人々の支援や権利保護に取り組み、当事者に寄り添った弁護士を目指します。また、自分が地方出身であることもあり、地方自治体の高齢者福祉、障害者福祉の改善などに携わりたいです。加えて、法律関連の仕事以外にも地方と都市部の教育格差改善に貢献できるような事業を立ち上げることも考えています。
東京都出身 薬学部2年
①この度は、奨学生として採用いただいたこと、ご支援くださっている維持会員の皆様に心より感謝申し上げます。貴奨学金のおかげで、経済的な不安が軽減され、安心して勉強や大学生活に打ち込むことができます。また、維持会奨学生として採用していただいたことは大変光栄なことであり、とても嬉しく思います。維持会員の皆様のご支援のおかげで私の大学生活が成り立っていることをしっかりと自覚し、大学で学べることすべてを吸収できるよう今まで以上に努力いたします。そして、維持会員の皆様が私たちの様な学生を助けてくださっているように、私も将来薬に携わる者として、困っている人たちの力になれる、社会に貢献できる人材になりたいです。
②機能生理学や代謝生化学という授業がとても興味深いです。機能生理学は生体各器官の生理機構に、代謝生化学は生体内分子の代謝様式に焦点を当てて生命現象の仕組みについて学ぶ科目です。また、それらの異常がどのような疾患へと結びつくのかも学びます。私は薬が人や動物などにどのように作用するかずっと不思議に思っていたので、薬が効く対象である生命現象を分子レベルで理解していくことで、薬が効く仕組みが少しずつ解き明かされていく感覚があり、とても楽しく感じています。これらの科目は、これから薬の作用機序を学ぶ際の土台となる知識であると思うので、しっかりと理解して吸収したいです。
③慶應義塾大学薬学部・薬学研究科が設置する、海外での研修や実習を行うプログラムに参加したいです。私は、将来、薬剤師になりたいのか、研究者になりたいのか迷っているのですが、どちらにせよ国際的な視点を持った医療人に成長したいと考えています。そのためにそれらのプログラムに参加して、海外の医療現場を実際に見て、国際的な医療品開発や薬学の役割を学ぶことで、国際的に通用する視点や知識を得たいと考えています。また、海外での経験を通して自分の内向的な性格を改善したいです。それらのプログラムに必要な英語力は、将来医療人として当たり前に求められると思うので、英語の勉強にも力を入れたいです。
④まだ具体的に定まってはいないのですが、人々が健康に、かつ、快適に日々を過ごすためには必要不可欠である薬に関する職業に就くことで、人々の日常を支える人になりたい、という将来の夢があります。前述しましたが、私は薬に対して研究者として携わるか、薬剤師として携わるか迷っているのですが、最近は研究者として薬に携わりたいという思いの方が強くなってきております。私には病気に苦しむ人々を救えるような薬を生み出すことで、社会に貢献したいという思いがあります。そのために大学では薬学の基礎から応用まで幅広く学び、さらに大学院へと進学して専門的な研究に取り組みたいと考えています。
新潟県出身 経済学部3年
①慶應義塾大学維持会奨学生に選んでいただき、大変光栄に思います。これは、学業と課外活動の両面で真摯に努力してきた証だと受け止めております。この奨学金は、経済的な支援に留まらず、慶應義塾の一員として、将来社会に貢献する人材となることへの期待であると強く認識しています。今後は、維持会の皆様の温かいご支援に応えるべく、これまで以上に学問に励み、躰道部での活動やゼミでの研究を通じて、自身の能力を最大限に高めていく所存です。常に感謝の気持ちを忘れず、義塾の発展に寄与できる人材となれるよう精進してまいります。
②私が大学生活で最も興味を持ち、深く学びたいと考える授業は、マーケットデザインやゲーム理論を専門とする津曲ゼミです。日吉キャンパスでのミクロ経済学の学びを通じて、市場や意思決定を数理的に分析する面白さに強く惹かれました。特に、ゲーム理論が実社会の様々な事象に結びついている点に深い関心があります。このゼミでは、経済学の理論を現実のビジネス課題に応用し、論理的思考力と戦略的な意思決定能力を養いたいと考えています。オープンゼミでの活発な議論とアットホームな雰囲気にも魅力を感じており、自身の数学的素養を活かして、この分野での学びを一層深めていきたいと強く願っています。
③今後学生時代で最もチャレンジしたいのは、ゼミでの研究を深め、その成果を社会に発信することです。私のゼミではマーケットデザインやゲーム理論を研究しており、これらは実社会の意思決定やビジネス戦略に応用できる非常に興味深い分野です。特に、個人の最適な選択が必ずしも全体の最大効用をもたらすとは限らないというゲーム理論の概念に強く惹かれています。今後は、輪読やグループディスカッションを通じて理論を深く理解し、現実のビジネス課題に応用する力を養いたいです。また、研究成果を積極的に発表し、多様な意見交換を通じて、多角的な視点を養い、自身の専門性を高めていきたいと考えています。
④卒業後は、ITコンサルタントとして企業の変革を支援し、社会全体の発展に貢献することが私の夢です。特に、企業の重要な変革期において、ITを含む多角的な視点から本質的な課題を解決し、その成長に深く貢献したいと考えています。躰道部で培った、目標達成に向けた粘り強い試行錯誤とチームで高め合う経験は、複雑な経営課題に向き合う上で不可欠な学びとなりました。お客様と「真のパートナー」として併走し、表面的な課題の奥にある「真の課題」を深く掘り下げ、ITとコンサルティングの専門知識を融合させて最適なソリューションを提供したいです。お客様の期待を超える価値を創造し、持続的な企業成長に寄与することが私の目標です。
長野県出身 理工学部4年
①このたび維持会奨学生に選出いただき、大変光栄に存じます。今後は、将来私自身が義塾に貢献できる立場となった際には、同じように支援する側として恩返しをしたいと強く感じております。昨年度も選出いただき,生活環境が大きく改善しました。昨今の物価高騰に伴い,私の最寄りのスーパーでも値上げが頻繁に行われ,食事を制限せざるを得なかった一昨年に比べ,極度に金額を気にして食事をとる必要がなくなり,健全な食事と交友関係を保つことができるようになりました。本当に感謝しています。今後も奨学生として自覚をもち,塾生の模範となるような品格ある振る舞いを心掛けたいと考えております。
②私は今,大学院への進学を前提に大学院の先取り授業を受講しています。それらは英語で講義が行われるため,英語力向上という意味でも全ての授業が刺激的です。その中でも特に,機械学習に関する「機械知能」という講義に最も関心があります。私が所属する研究室でも機械学習を扱っており、より専門的かつ実践的な知識を深めたいと考えております。この講義では,英語のネイティブ話者との積極的なディスカッションの機会が設けられており,技術的話題に関して英語で討論するという経験を積むことができる点でユニークで,毎回の講義に意欲的に取り組めています。
③自分にとって心地よい環境に甘んじることなく、妥協せずに新たな挑戦を続けていきたいです。具体的には,例えば交流という面で言えば,研究室という環境にいると,研究室のメンバーとの交流に閉じる傾向にありますが,学外の方々とも積極的に交流を図り,多様な価値観や知識を吸収したいと考えています。また,言語という面でも,些細ではありますが研究室の留学生と積極的に英語でコミュニケーションをとるといった地道なチャレンジを積み重ねていきたいと考えております。
④卒業後は博士課程へ進学し、その後は企業の研究者として、社会に直接的なインパクトをもたらすプロダクトの基盤となる技術開発に携わりたいと考えています。特に,私は,機械学習を学んでいることから,機械学習がコアとなるようなプロダクトをこの世に生み出したいです。現行のプロダクトで,本質的に機械学習がユーザに価値を提供しているものはごく僅かだと考えています。その中で,技術が本当に社会にブレイクスルーを引き起こすようなものを作ることが私の夢です。
愛知県出身 文学部2年
①ご支援いただけることを非常に光栄に思います。そして、今私が皆様に支えていただいているように、将来は自分自身も慶應義塾で学ぶ後輩たちを支えられるように、慶應義塾での学びを社会に還元できるように、学業、課外活動のいずれにおいてもより一層努力していく所存です。また、私は地元を離れて暮らしており、学費に加えて生活費の面でも両親に大きな負担をかけているのが現状です。そのような中で、このたび奨学生としてご選出いただいたことにより、両親の経済的負担を軽減できること、そして自分がアルバイトに費やしていた時間を学業や課外活動に充てられることは、私の学生生活において非常に大きな意味を持ちます。支えてくださる皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。今後も奨学生としての自覚を胸に、恵まれた慶應義塾の環境を最大限に活かしながら、常に自分が成し遂げたいこと、そして慶應義塾や社会の中で果たすべき役割とは何かを問い続け、学生生活を全力で駆け抜けてまいります。
②「現代英語学」という授業です。この授業では、言語学の歴史やことばを観察する際の言語学的な視点を学びます。この授業を通して、普段の生活で当たり前に使っている日本語や英語のことばを見つめ直し、「私たちはなぜこのようにことばを使っているのか」と当たり前の裏側にあるロジックを考えることの楽しさを知ることができました。また、日常生活の中で身の回りに溢れていることばに積極的に目を向けるきっかけともなりました。教授から学会でのご経験や授業内容に関連する研究のお話も伺うことができ、毎週の授業がとても楽しみです。この授業以外にも興味のある授業ばかりで時間割が構成されており、毎日が刺激に満ちています。特に、一見関係のなさそうな授業同士に共通点やつながりを見いだせたとき、学びが多方面に広がっていることを実感できて嬉しくなります。
③海外提携校への交換留学に挑戦したいと考えています。慶應義塾内には素晴らしい学びの環境が整っていますが、さらに外の世界に飛び出し、留学先ならではの授業や、そこでしか出会えない人々との交流を通して、慶應義塾での学びをより発展的なものにしていきたいです。交換留学を実現できた際には、現在学んでいる文学や言語学の理解を深めるとともに、マイノリティ民族への教育政策や異文化理解についても学びを広げたいと考えています。さらに、大学入学後に経験した国際寮での生活や、異文化理解に関する授業の受講を通して、高校時代の海外経験とは異なる感覚や視点から異文化に触れることができるのかを、実際の体験を通じて確かめたいです。また、来年の冬には内閣府の「世界青年の船」事業に参加し、多くの海外青年と船上で共同生活を送る予定です。船という特定の国がホームにならない環境での国際交流から、自分が将来貢献したいと考えている教育分野での環境構築に何か還元できることがないか、模索していきたいです。
④卒業後は、学部での学びをさらに深めるために大学院に進学したいと考えています。そして、その先は何かしらの形で教育における国際文化交流の促進や異文化理解に貢献したいと考えています。そのために、私が今学びの軸足を置いている、文学や言語学、教育学、異文化コミュニケーション、それぞれの分野に橋をかけて、自分がどのように教育に、社会に貢献することができるかをじっくりと時間をかけて見極めていきたいです。人々が自分とは異なるバックグラウンドを持つ人の行動や言動を表面的に捉えるのではなく、その行動の背景にはどのような文化や考え方、価値観があるのかというところまで理解しようと努め、歩み寄れる社会を構築することが大きな目標です。
大阪府出身 文学部4年
① 採用いただいたことに深く感謝しています。現在私は「地方女子の進路の選択肢を広げる」ことを目標に、非営利団体MORE FREEを設立し、都内で地方出身の女子学生向けシェアハウスを2軒展開しています。このような実践活動を続けながら学業と両立できるのは、維持会の皆様のご支援あってこそです。ご期待に応えるためにも、社会課題の解決に向けて責任を持って行動します。将来的には維持会奨学生を支える側になれるよう、進化してまいります。奨学生として恥じぬよう、日々の学びや実践に真摯に取り組み続けます。
②研究室でのゼミ活動が最も興味深く、楽しい時間です。 統計社会学を中心に学ぶ中で、特に家計や家族に関するデータを分析することに熱を注いでいます。現在は、経済格差や地域・性別による進学格差をテーマに卒業論文を執筆しており、統計的な視点から社会課題を可視化することの重要性を実感しています。数字を通じて「見えにくい困難」を明らかにし、それを社会に発信することで、政策提言や実践活動にもつなげたいと考えています。今後も理論と実践をつなぐ学びを深め、現実社会に還元できる力を身につけたいです。
③今年度中に、MORE FREEの第3号となるシェアハウスの開設を目指しています。外部団体との連携や寄付者の開拓、業務のマニュアル化を通じて、より持続可能な組織づくりに挑戦したいです。また、研究面では卒業論文に全力で取り組み、進学格差の現状をデータで示すことにより、課題の本質に迫りたいです。将来的には、研究で得た知見を社会に発信し、制度や意識の変革にも貢献していきたいです。残された大学生活を、より実りあるものにしていきます。
④卒業後は企業に就職し、社会での実践力と信頼を培いたいと考えています。将来的には、MOREFREEの活動をライフワークとして継続し、10年後には都内に10軒のシェアハウスを展開したいです。さらに30歳までに独立し、地方の女性が自分らしく、前向きに働ける社会を実現するためのサービスを立ち上げたいという夢があります。まずは社会の中で課題解決に向けたスキルを磨き、仲間と共にビジョンを形にしていきたいです。原点となる「誰かの選択肢を狭めない社会」を目指して、一歩ずつ歩んでいきます。
島根県出身 商学部4年
①一昨年度に引き続き、慶應義塾維持会の奨学生にご採用いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。維持会の皆様方のご支援があって、今こうして学びに集中できていること、そして、「やってみたい」と思うことのほとんど全てに挑戦できていること、感謝申し上げます。今後も感謝の気持ちを忘れず、将来的には私が誰かを支えられるよう、学業と課外活動の全てに全力で取り組んでいく所存です。
②現在履修している中で最も関心を持っているのは、ビジネスモデルを中心に学ぶマーケティングの授業です。この授業では、デジタル化や人口動態の変化、グローバル化といった絶えず変化する市場環境を踏まえ、企業がどのように新たな価値を創造し、持続的に成長するための戦略を立案すべきかを学んでいます。加えて、スタートアップ企業の新規事業開発や、既存企業が従来のビジネスモデルから脱却して新市場を開拓するケーススタディも取り入れられており、理論と実践の両側面から学びを深めています。
③今夏のケンブリッジ大学での短期留学において、専攻予定の「国際経営」について英語で自己表現をする力を高めることです。昨年度もアメリカで学ぶ機会を頂きましたが、英語の発信力はもとより、そのために必要な基礎知識が圧倒的に不足していることを痛感しました。この悔しさを糧に、今回は事前に関連する専門書や論文を読み込み、また、現地文化や現地企業についての見識を深めたうえで臨みたいです。その上で、身に付けた知識を基に、自分の考えを臆することなく堂々と伝えたいと思います。そして最終的には、ケンブリッジでの学びや現地の学生との共同研究で得た知見や経験を活かし、「日本企業の海外展開における成功要因の分析」という卒業論文を完遂したいと思います。
④正直なところ、現状何も決まっておりません。ですが、「人を育てる」教員という職業に就きたいという気持ちは固まっております。社会が急速に変化しているからこそ、その社会を下支えする人材を学校教育で育成していきたいと考えます。教職を目指す学生は慶應の中では稀かもしれません。しかし、慶應に入学し、自分にはない類まれな経験や知を持つたくさんの仲間と出会い、刺激を受けて視野が広がる中、教育の重要性を再認識しました。「社会の先導者たれ」という慶應義塾の理念に対して、教育の立場から貢献していく所存です。生徒一人一人の「将来」を形成する「今」に少しでも良い影響を与えられるよう、今後も精進して参ります。
広島県出身 法学部1年
①この度は慶應義塾大学維持会奨学生にご推薦いただきましてありがとうございます。慶應義塾大学に入学してからは個性的な塾生や教授に囲まれ、生活面・勉強面共に充実した日々を過ごすことができています。難病を抱える父の負担を少しでも軽減できるようにアルバイト等で生計を立てる必要がありますが、今回奨学生として選んでいただいたおかげで、精神的・経済的な不安を払拭し、将来の夢である法曹への第一歩となる司法予備試験のために専念できる時間を整えることができるようになりました。
維持会奨学生に選んでいただいた以上は、日々、恥じぬよう精一杯活動してまいります。また将来、自分も維持会奨学生を支える立場になりたいと思います。
②法学部生ではありますが、今一番熱中しているのはアラビア語の授業です。今年から始まったインテンシブコースを履修しているため、週四日の授業と復習の時間を合わせるとほぼ毎日アラビア語に触れています。日本でアラビア語はマイナーな言語である一方、日本に住むアラブ人は年々増加しています。先日、日吉キャンパスに開所したアラビック・ラーニングセンターの開所式典では、UAE国務大臣によるご講演に加えアラブのお菓子を堪能したり、アラブ圏の留学生とも親しくなったりとアラブ文化にたくさん触れることができました。今後、アラブ圏にかかわるような仕事が増えてきたときに、言語や法律がトラブルを未然に防いだり、チャンスを掴む一助になればと考えています。
③入学を機に関東に移り、首都圏の熱量やスピード感、都市格を実感するとともに、地元にしかない魅力を再発見することにもなりました。
私の故郷岡山には「うらじゃ」という祭りがあります。岡山が桃太郎伝説の発祥とされることにちなみ、温羅(うら=鬼)化粧を楽しんだり踊ったり、30~40万人を動員する夏の風物詩として今年30回目を迎えます。また、大学と連携し、学生が授業の一環として企画運営する会場があったり、授業とは無関係でも参加する学生や若手に裁量を与えたりして祭りを創り上げています。
勉学に励むのは勿論ですが、大学のサークル活動も楽しみながら充実した4年間にしたいと思っています。その上で、「うらじゃ」に参加して故郷を盛り上げながら経験の幅を広げたいと思います。
④私は多くの人の悩みに寄り添い、うつむいている人を前に向かせられるような法曹になりたいと考えています。紛争を未然に防いだり、起きてしまった紛争を解決したりすることで、円滑な企業活動や従来の生活を取り戻す手助けができる点が魅力的であり、正義感が強く傾聴力のある私の性格に合っていると感じるからです。また、英語やアラビア語を活かして国際社会で活躍する外交官にも興味があります。アラブ人留学生と交流したことは、他国との利害を見極めながら架け橋になりたいと思うようになりました。自分の可能性を信じて将来の選択肢をひとつでも多く残しておきたいので、夢をひとつに絞るのはもう少し先になりそうですが、夢が明確になったときに掴める自分であるために日々懸命に努力します。
海外出身 環境情報学部2年
①I am very grateful and delighted to have been selected. It is a big responsibility but this opportunity motivates me to study harder and in the long term contribute more to society. As an international student from Indonesia, I realize that living and education costs in Japan are considerably higher than Indonesia. To offset this I have tried to relieve the burden from my family as much as I can. In particular since my second semester, I have been covering my living expenses entirely with scholarship and part time money.
Last semester, I worked a part time job twice a week, but this semester my class schedule only allows me to do it once a week. At the same time, I have had extra expenses, such as purchasing robotic parts and attending class related activities such as kenkyuukai gasshuku. So, I am extremely grateful that I got this scholarship.
Moreover, I look forward to the opportunity to join Iji-kai gatherings. I believe it will be a valuable chance to meet inspiring people, share experiences, and build meaningful connections that will help me grow both personally and professionally.
②I am most interested in classes and research related to IT and biology. That is why this semester I have joined Suzuki Haruo’s research lab. In his lab, we do research on microorganisms like bacteria and plasmids. Bioinformatics combines my interest in IT and biology, and has great potential to contribute to society, especially in the healthcare sector, which I am really passionate about. In particular, I am interested in researching AMR (Antimicrobial resistance) on Acinetobacter baumannii, a high priority bacteria in the WHO pathogen list. Through bioinformatic analysis, we can get more insights about its mechanisms and spread, which can help in drug development and outbreak controls. Further I have taken professor Haruo’s introductory classes, such as “Data Science for Genome Dynamics” and “Data Science for Bioinformatics”. Both were really interesting and provided crucial insights on the basics.
In addition to that , I am interested in general computer science and related IT classes, especially those that involve hands-on projects. For example, simulating optimization in “Computer Architecture”, predicting relationships from step tracking data in “Emergence of Data Driven Society”, and making a game with python in “Fundamental of Information Technology II”. Ultimately, I enjoy learning how different technologies work together to solve real-world problems.
③Firstly, I got an internship in Mitsubishi Fuso which will last for 6 months, starting from August to January. This means that for the first half of next semester, I have to balance internship work with studies, committee work, and circle. It might be tough but it will be a great learning experience. In the internship, I will get training and working experience on data analysis and management.
Secondly, I want to take my Japanese to the next level. Hence, I am aiming for JLPT N2 next year. Right now, I am trying to study new vocabularies everyday and read Japanese media regularly. I also try to speak Japanese to my dorm and orchestra friends whenever possible. Hopefully, with this effort I will be able to take some academic classes in Japanese next year, expanding my options and opportunities, especially in the field of biology. Additionally, I am considering going to BioCamp in Tsuruoka for 1 semester next year, to gain wet lab experiences.
Lastly, I want to challenge myself to do self studies related to biology basics. This semester, it wasn’t always easy to follow discussions because of the width of the field. For example I have been reading new literature in parallel to taking the class “Introduction to Molecular Biology 1 and 2”, not only to keep up with class content, but also to build a stronger foundation for advanced research papers.
④In the long term, I wish to be involved in projects related to healthcare technologies that improve human health and society’s quality of life. One way to achieve this, is by continuing my bioinformatic research on AMR, in turn contributing toward more efficient drug developments. However, it could be by following other paths as well. Healthcare software, AI integration into medical diagnosis, and alike all sound interesting to me at this point.
After graduation, I first want to gain work experience in an IT company in Japan. This is because modern healthcare solutions heavily rely on information technology. Through this occupation, I wish to build a strong foundational knowledge of programming, data analysis, software integration, etc. Thereafter, I am considering studying for a masters degree in either bioengineering, bio consultancy, or bioinformatics. After all, I am very interested in working in technological research and development for a company in the health sector and most jobs would require me to have extensive research experience as enabled by a masters degree in those fields.