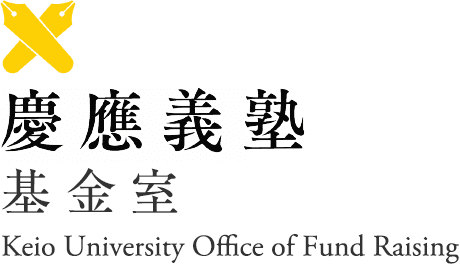新潟県出身
この度は、私を慶應義塾維持会奨学生に採用していただき本当にありがとうございます。私には姉妹が二人おり、私たちが成長するにつれ家計の困窮は深まるばかりでした。昨年度は貸与奨学金とアルバイトで稼いだお金で何とか生活を維持することが出来ましたが、せっかく慶應に在籍しながらも思うように学業や課外活動に打ち込むことができずやるせなさを感じるとともに、家計が厳しい中で慶應進学を許してくれた家族への申し訳なさも常に抱いていました。そういった状況の中で、今年度維持会のみなさまから厚いご支援を賜り、家計の負担を和らげることができますことを非常に嬉しく思います。
私には、将来は海外で経済学博士号を取得して経済学者になりたいという夢があります。その夢に向かい、昨年度は慶應の国際的な環境を活かすべくオールイングリッシュの授業を複数履修し、英語を使ったプレゼンやディスカッション、アカデミックライティングの素地を築きました。履修生のほとんどが留学生や帰国子女といった授業も多かったため、国外に出たこと自体ほとんどない私は挫折の連続でしたが、ほかの受講生や先生方とともにお互いのバックグラウンドだからこその切り口から意見交換をすることができたほか、プライベートで仲良くする留学生の友達も作れたため、日本にいながらも貴重な学習機会が得られました。
今年度は経済学の勉強により注力したいと考えています。必修科目のミクロ経済学や経済史に加え、数学・統計・金融の関連科目を重点的に履修しており、これから経済学を探究するために必要な道具を身に着けること・学術と実用の両方向から経済活動について知見を得ることを目指しています。また、これまでの慶應での学びを活かしてさらに成長するため、課外活動では即興英語ディベートサークルに所属しており、これまで3度大会に出場しプライズをいただくこともありました。昨年冬からは金銭的な都合でやむなく活動休止しておりますが、今年は活動を再開していまだ果たせていないチームでの予選突破を目指したいと考えています。
最後になりましたが、維持会のみなさまからご支援をいただけますことを心より感謝申し上げます。今年度はよりいっそう勉強や課外活動にも打ち込み、将来は慶應に恩返しができますよう努めてまいります。
新潟県出身 経済学部2年(2024年度)
この度は慶應義塾維持会奨学金の奨学生として採用していただき誠にありがとうございます。私の家庭は4人兄弟であり、それぞれが大学に通っていたり、進学を希望していたりします。兄弟それぞれの学費や一人暮らしの費用を合わせると、大変な金額になり、これからますます増えていきます。ご支援のおかげで、集中して学業や大学生活に励むことができるようになりました。
私は大学での一つの目標として、公認会計士試験の合格を目指し、学習しています。実際に公認会計士として働くことを想像すると、語学力やさまざまな分野の知識、会計制度の本質的理解、異なる分野を専攻している塾生の意見、交流の場など、大学での学びは非常に大切で貴重なものです。慶應義塾維持会について詳しく調べていくうちに、奨学金事業だけでなく、こういった大学のさまざまな学びにも皆様のご支援があったことを知りました。慶應義塾のさらなる発展を願って活動されている皆様と同じよう、一人の未熟な塾生ですが頑張っていきたいと思うと同時に、大学での学びひとつひとつを大切にしていきます。また、大学での生活はまだ二カ月が過ぎたばかりですが、今まで知らなかったバックグラウンド、考えを持つ人達と会いました。日々驚くと共に新しい可能性に胸を躍らせています。こうして、交流することのできる環境はとても貴重で、活かさなくてはもったいないです。コロナ禍での生活を経て改めて強く思うようになりました。大学で出会った仲間ひとりひとりを尊重すると同時に、私自身の考えもより豊かにしていきたいです。学外の場では、宇宙開発を経済的・政策的に研究する団体に所属して活動しています。そのときに強く思うのが、科学的なハードの側面と制度的なソフトの側面がともに成長しないと、先端分野の成長が困難であるということです。そういった点からも、商学部生である私も、商学部設置科目として、文理を越えた分野を学ぶことのできる環境がとても豊かだと感じます。維持会の皆様のおかげで得られるこの豊かな環境を精一杯活かして、日々励んで参ります。本当にありがとうございます。
新潟県出身 商学部1年(2024年度)
この度は、慶應義塾維持会奨学金に採用していただき誠にありがとうございます。父の転職により家計の収入が減少し、大学の学費や一人暮らしの費用などを考えると両親への経済的負担が大きくなり、金銭的に不安を感じていました。また、私には弟が二人おり、大学受験、進学を控え今後さらに経済的負担が大きくなります。そこで、今回ご支援いただきましたことを家族一同心より感謝しております。
私は、現在大学にて主に物理学を中心に学んでいます。量子力学や波動,電磁気学など物理学について幅広く学んでいる状況です。学部1年生時代に物理学を学んでいましたが、学部2年での授業はどの授業も内容が高度で理解が難しいですが、授業とその後の復習を通して少しずつ理解を深めています。また理工学基礎実験にて専門である物理学の実験はもちろん、専門外である化学の実験も行っており、どの実験もとても興味深く楽しい実験ばかりです。レポートの作成は大変ですが、実験についての理解を深めるため、また将来に論文などを書く際に役立てられるように丁寧に取り組んでいます。休日の日には授業の課題に取り組むことはもちろんですが、空いた時間を友人たちとともに博物館や水族館などの学びを深められる場所へ出かけたり、私の趣味である東京や神奈川の町へ散策に出かけたりと充実した日々を送っております。
今後は、私の将来の目標である海洋の研究者になれるよう物理学、特に液体についての物理学を学んでいきたいと思っております。海洋の研究者の中でも、特に海洋の資源開発についての研究を行っていきたいと思っております。この研究内容は、幼いころから私が興味をもっていた海洋を探求できることに加え、資源を外国に頼りきっている日本の状況を少しでも改善でき、社会貢献へとつなげることができるかもしれないと考えています。具体的には、日本近海にねむっている、次世代のエネルギー源として注目されているメタンハイドレートを安定して採掘することができる技術を探求することです。現時点ではこの研究内容が、自分の興味を満たせ、かつ社会貢献できる、私にとっての最適な研究内容であると思っております。
最後になりましたが、改めてご支援いただき心から感謝しております。皆様からのご支援のおかげで今後より充実した学生生活を送ることができます。今後も奨学生および塾生としての誇りを持ち、より一層勉学や課外活動に取り組んでまいります。
新潟県出身 理工学部2年(2024年度)